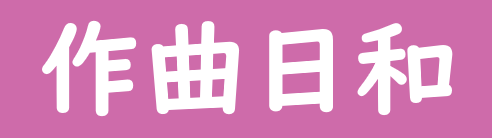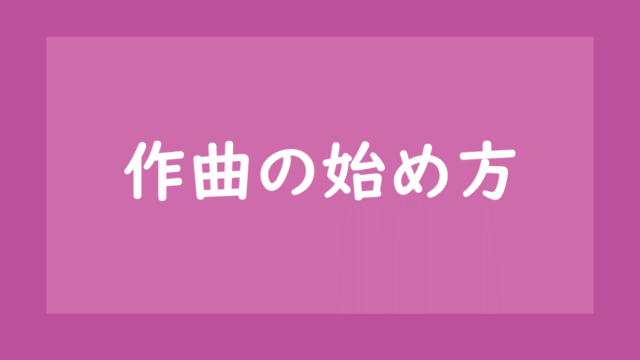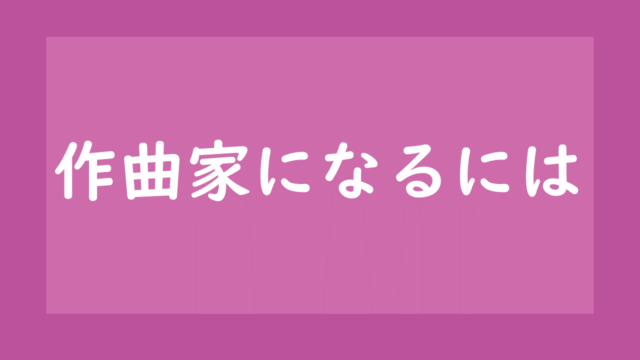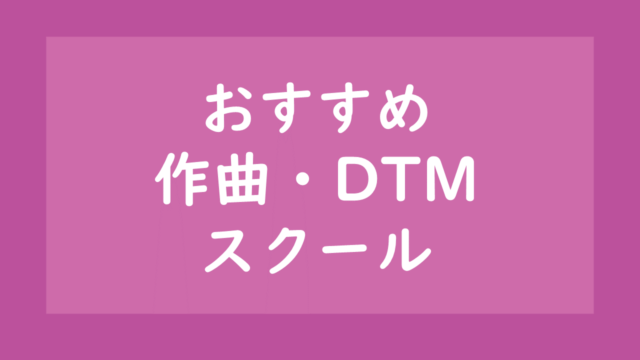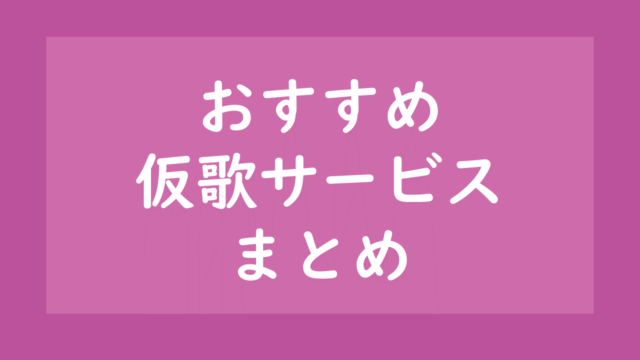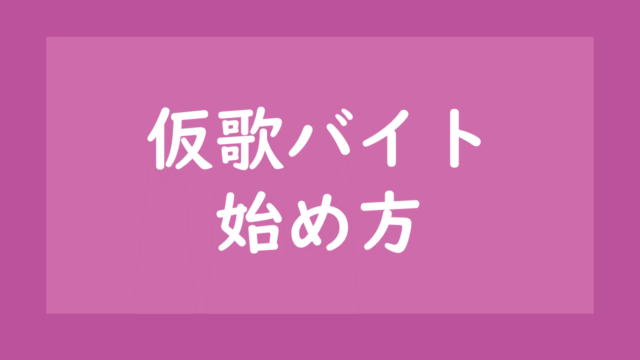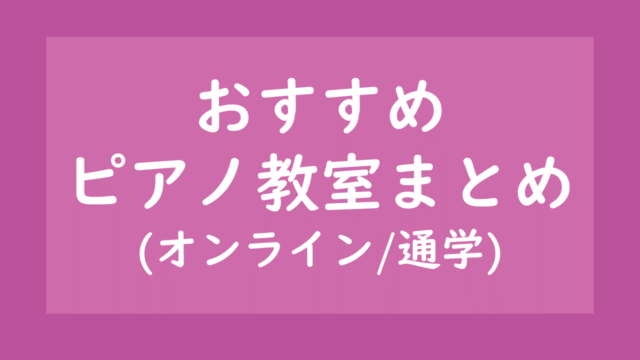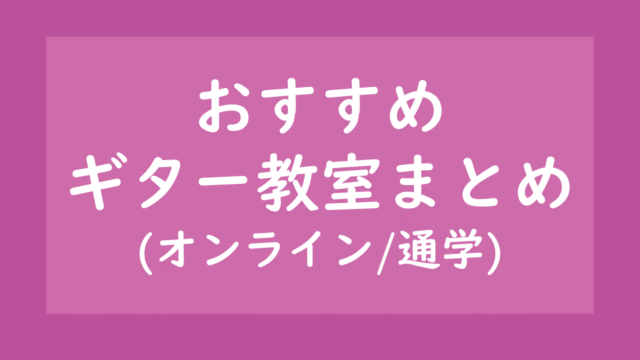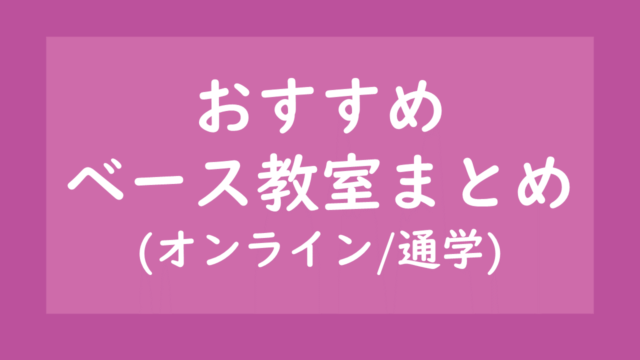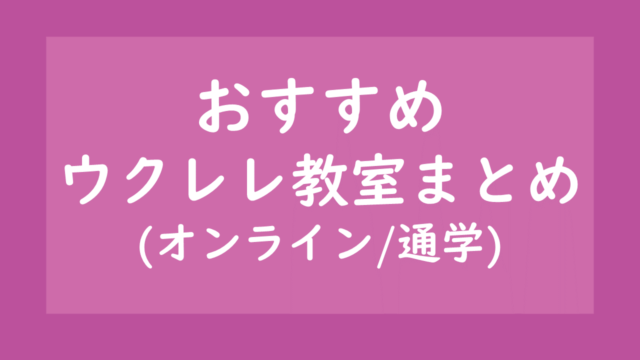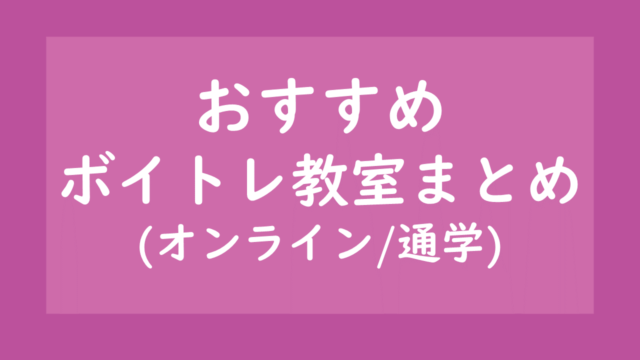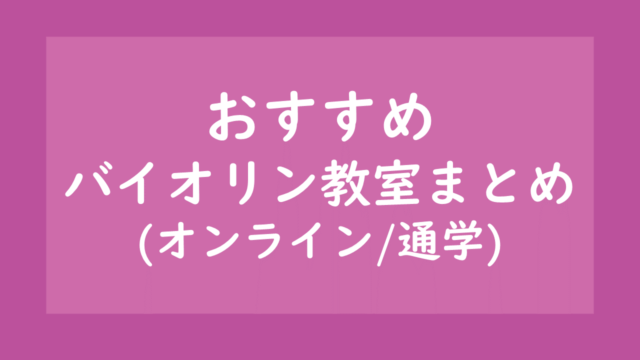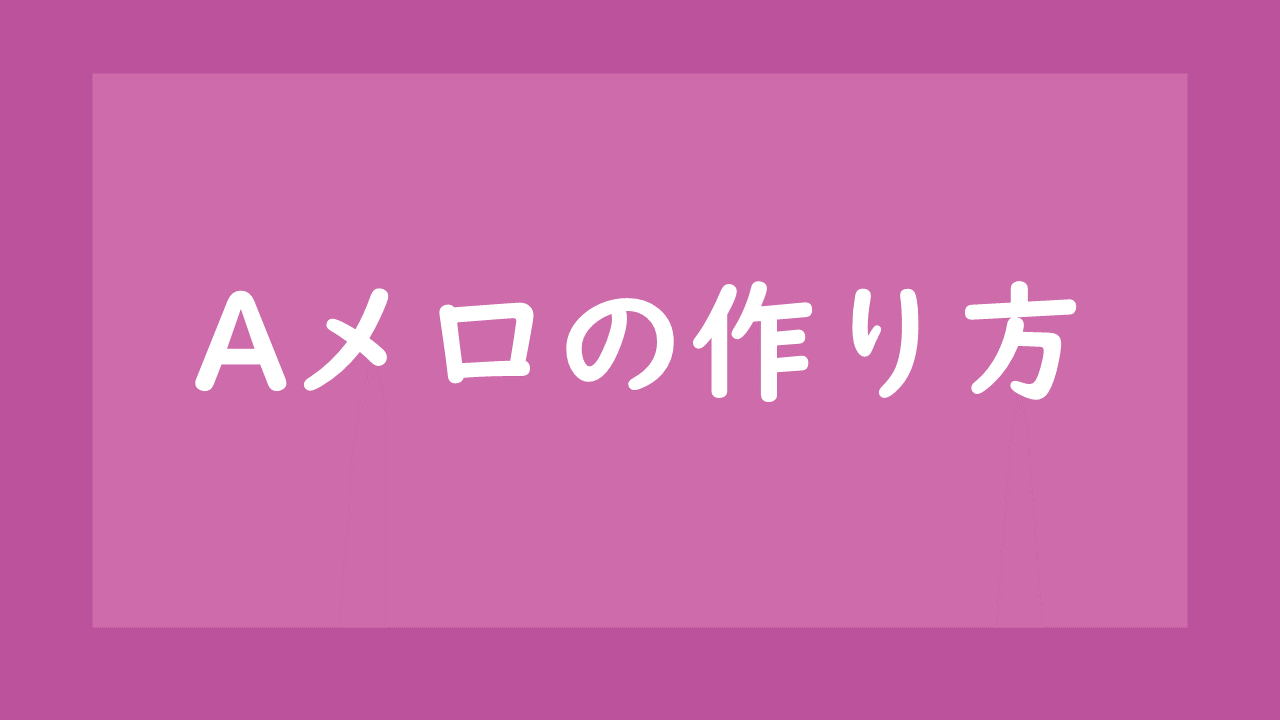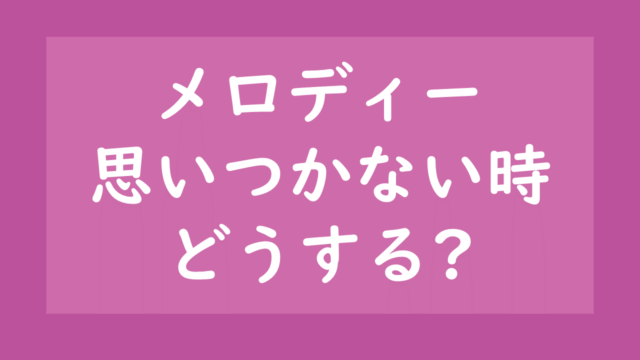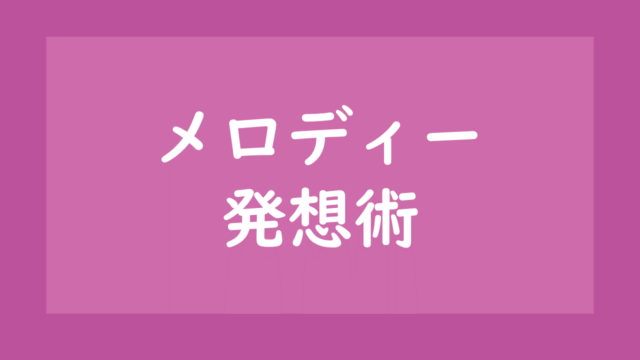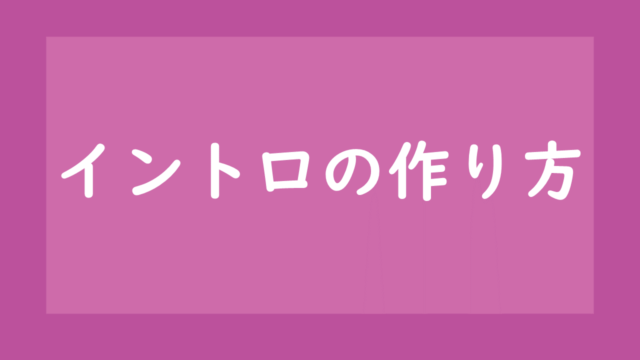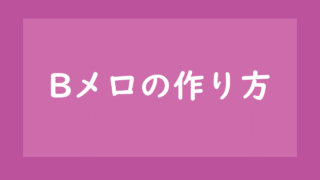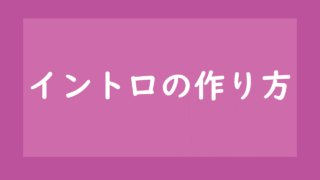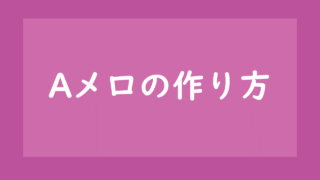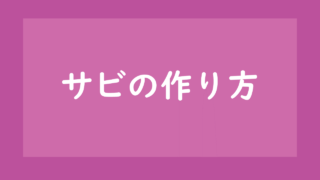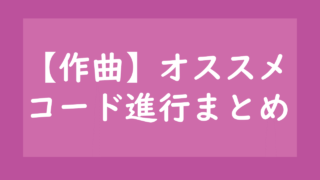・Aメロの作り方を教えて!
・AメロからBメロへのつなぎ方も知りたい!
・作曲してて、Aメロ作りが一番難しいと思うんだけど、コツとかないかな?
このような方向けの記事になります。
本記事の内容
- 楽曲におけるAメロの役割
- 【作曲】Aメロの作り方とおすすめコード進行を紹介!【初心者〜中級者向け】
- Aメロ作りのコツ
■ 楽曲におけるAメロの役割

楽曲を一つの物語と考えると、Aメロは序章です。
リスナーにその後の展開を期待させられるものを作る必要があります。
もし、Aメロの時点で「つまらなそう」と思ったら、最悪、そこで聴くのをやめてしまうかもしれません。
楽曲は大きく「イントロ、Aメロ、Bメロ、サビ、間奏、アウトロ」のブロックで成り立っています。
各ブロックごとの「作りやすさ」は人によって違いますが、Aメロ作りが難しいと感じる人は多いようです。
その理由は歌の音域にあり、Aメロは盛り上げ過ぎないよう、なるべく狭い音域(目安:1オクターブ以内)で作らなければならないからです。
もちろん、Aメロが1オクターブ以上の音域で作られている楽曲も存在しますが、作曲をはじめたてのうちは1オクターブ内で収めるよう心がけましょう。
■【作曲】Aメロの作り方とおすすめコード進行を紹介【初心者〜中級者向け】

それでは、「Aメロの作り方」を以下の手順に沿って解説していきます。
手順①:Aメロの長さ(尺)を決める
手順②:コード進行を決める
手順③:コード進行に合わせてメロディを考える
手順①:Aメロの長さ(尺)を決める
まず、Aメロの長さ(尺)を決めましょう。
長さ(尺)は「曲の構成」と「小節数」で決まります。
曲の構成とは、
[例]
・ Aメロ→Bメロ→サビ
・ Aメロ→A’メロ→Bメロ→サビ
・ Aメロ→A’メロ→サビ
のような、楽曲の全体のブロックのことです。
ここでいう、A’メロは「Aメロと同じ(近い)メロディが繰り返されている場合」の呼び方です。
(※世の中の楽曲の2コーラス目(2番)では、「Aメロ」が省略されて「A’メロ」だけになっているパターンも多いです)
小節数は、
[例]
・ Aメロ(16小節)→Bメロ→サビ
・ Aメロ(8小節)→A’メロ(8小節)→Bメロ→サビ
・ Aメロ(8小節)→A’メロ(8小節)→サビ
のような各ブロックの内訳です。
作曲初心者の方は、「Aメロ(16小節)」や「Aメロ(8小節)→A’メロ(8小節)」あたりが良いと思います。
・ Aメロ(32小節)→Bメロ→サビ
のようにAメロが32小節もあると、曲が間延びしてしまい、退屈な印象になりやすいです。
手順②:コード進行を決める
曲の長さ(尺)(「曲の構成」と「小節数」)が決まったら、次はコード進行を決めましょう。
今回は例として「カノン進行(カノンコード)」を使用します。
C→G→Am→Em→F→C→F→G
※他の「オススメコード進行」もこちらの記事にまとめているので、
もし良ければ参考にしてみて下さい。
[例]
手順①の曲の長さ(尺)(「曲の構成」と「小節数」)を
・Aメロ(8小節)→A’メロ(8小節)→Bメロ→サビ
とした場合、「カノン進行」はちょうど8小節のコード進行なので、
・Aメロ(カノン進行)→A’メロ(カノン進行)→Bメロ→サビ
となります。
ここで気を付けたいのは「A’メロからBメロへのつなぎ方をどうするか」です。
つなぎ方は大きく分けて、
- A’メロの最後のコードをGにする (カノン進行そのまま)
[効果]→次のブロック(Bメロ)に繋がっていくような印象になる
[A’メロのコード進行] C→G→Am→Em→F→C→F→G (カノン進行そのまま) - A’メロの最後のコードをCにする (カノン進行の終わりを少し変えてCで終わらせる)
[効果]→Bメロにいく前に一度終わったような(着地した)印象になる
[A’メロのコード進行] C→G→Am→Em→F→C→F・G→C (カノン進行の終わりを少し変更)
の2つがあります。
もちろん、他のつなぎ方もあり、また、Bメロの最初のコードも繋ぎ方を決める重要ポイントなのですが、現時点ではまだBメロがないのでこの2つから選びます。
今回は、②A’メロの最後のコードをCにする (カノン進行の終わりを少し変えてCで終わらせる)のパターンで解説していきます。
手順③:コード進行に合わせてメロディを考える
ここまでの流れをおさらいしておくと、
手順①:Aメロの長さ(尺)を決める(「曲の構成」と「小節数」)
↓
Aメロ→A’メロ→Bメロ→サビ(曲の構成)
↓
Aメロ(8小節)→A’メロ(8小節)→Bメロ→サビ (小節数)
↓
手順②:コード進行を決める
↓
Aメロ(カノン進行)→A’メロ(カノン進行)→Bメロ→サビ (コード進行)
↓
Aメロ(C→G→Am→Em→F→C→F→G)→A’メロ(C→G→Am→Em→F→C→F・G→C)→Bメロ→サビ (A’メロの終わり部分を変更した実際のコード進行)
となっています。
コード進行が決まったので、メロディを作っていきましょう。
Aメロ(C→G→Am→Em→F→C→F→G)→
A’メロ(C→G→Am→Em→F→C→F・G→C)
まず、このコード進行をピアノやギターで弾いてみて下さい。
楽器が難しい方は↓に音源を用意したのでこちらをどうぞ。
コード進行に合わせて歌いながら、まずAメロ(C→G→Am→Em→F→C→F→G)のメロディを考えます。
A’メロ(C→G→Am→Em→F→C→F・G→C)のメロディはAメロの繰り返しなので流用しつつ、最後のコード変更した部分のみ新しいメロディを考える)
メロディ作りのポイントは、
・Aメロなので盛り上げすぎない
・なるべく1オクターブ以内の狭い音域で作る
・歌モノなので歌って作る(息継ぎを考慮)
です。
※コード進行に合わせてメロディを作る方法はこちらの記事で詳しく解説しています。
※メロディが思いつかない場合はこちらの記事もどうぞ。
■ Aメロ作りのコツ

ここまでAメロの作り方を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
Aメロは「狭い音域で盛り上げ過ぎない」といった制約があるため、プロの作曲家でも悩むことがあります。
作曲初心者ですと、それに加え「AメロからBメロに上手く繋がらない」などの問題も起こりやすく、つまずきやすいセクションと言えるでしょう。
Aメロ作りのコツは、他のセクション(イントロ、Bメロ、サビ等)と同様、既存楽曲を聴き込み、分析して「色々なAメロのパターンを知っておく」ことです。
・曲の構成
・小節数
・AメロからBメロのつなぎ方
・アレンジに使われている楽器
など。
実例を知っていると自信を持って使えますし、曲作りはメロディー以外は真似してOKです。
楽曲分析をしつつ、たくさん曲を作ってみて下さい。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
【作曲をされている皆様へのお知らせ】
【「作曲・DTM」オンライン無料体験レッスン」を受けてみませんか?】
「椿音楽教室」はオンラインレッスンを開講しており、ご自宅から一歩も出ずに「作曲・DTM」を学ぶことが出来ます。(※2024年現在)
↑↑「プロの作曲家・編曲家を目指している方」「今まで独学でやってきたけど、一度しっかり学びたい方」にオススメです!
【こちらの記事もどうぞ!】
【プロが解説】作曲の始め方をまとめました!【DTM・ギター・ピアノ】
【J-POP】作曲家になるにはどうしたらいいの?【独学OKです!】
【楽譜読めないOK】仮歌バイトの始め方まとめました!【在宅で稼げる・副業】
【作曲】メロディの発想法を11つ紹介!「作れない」を解消!【思いつかない(浮かばない)人向け】
【料金比較しました】ギターレンタルサービス厳選3社!【オススメのギターも紹介】