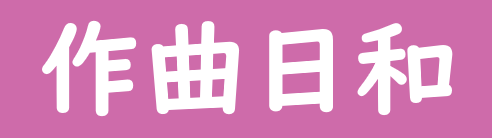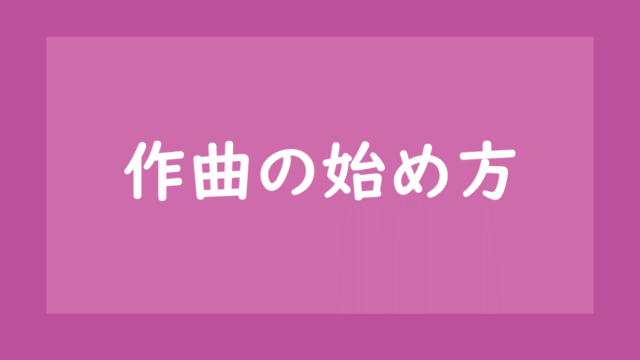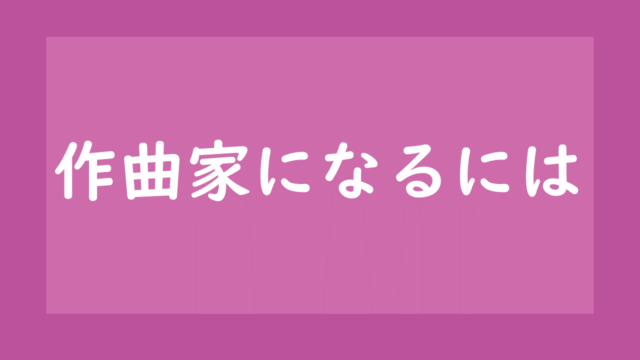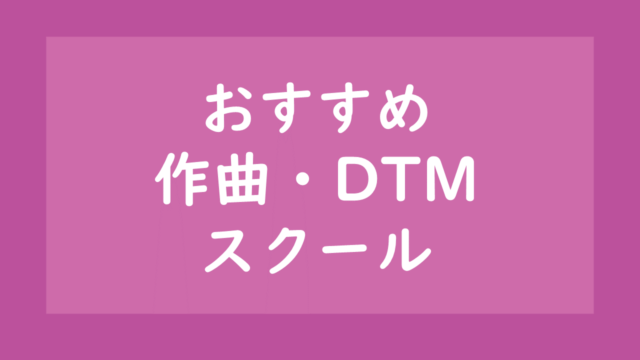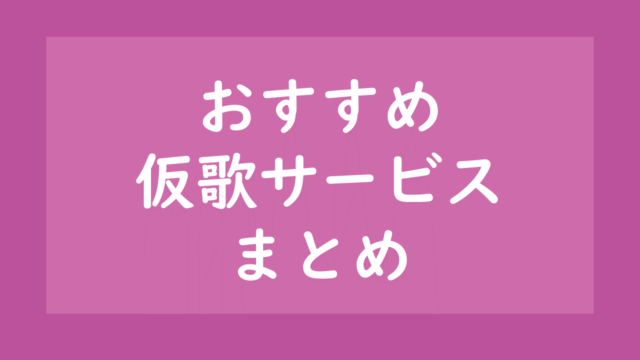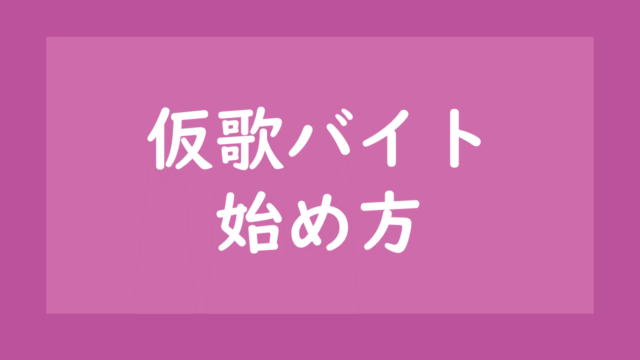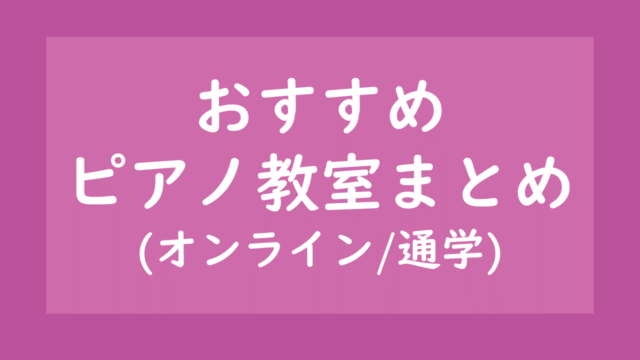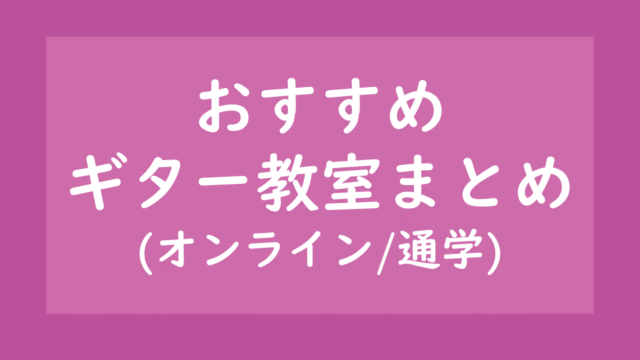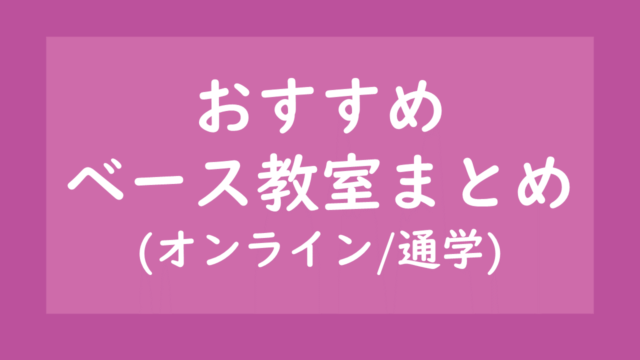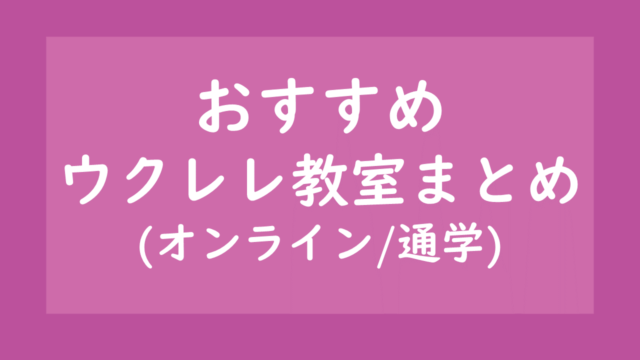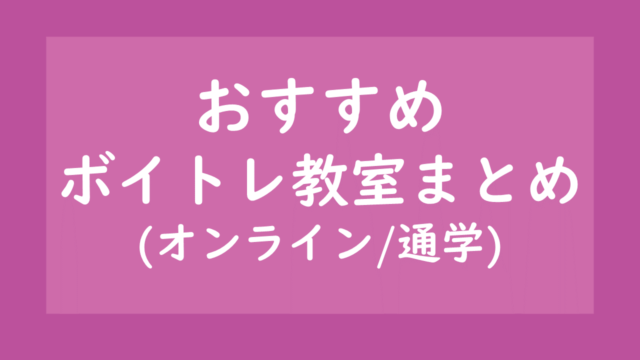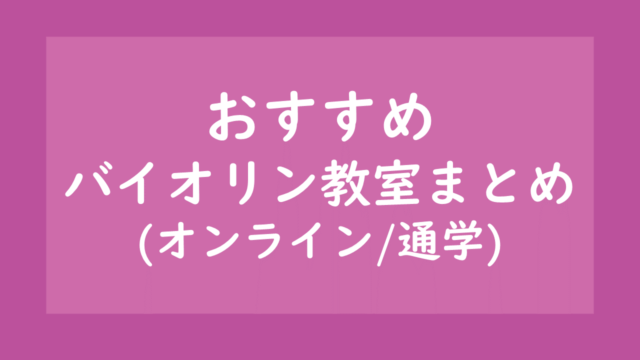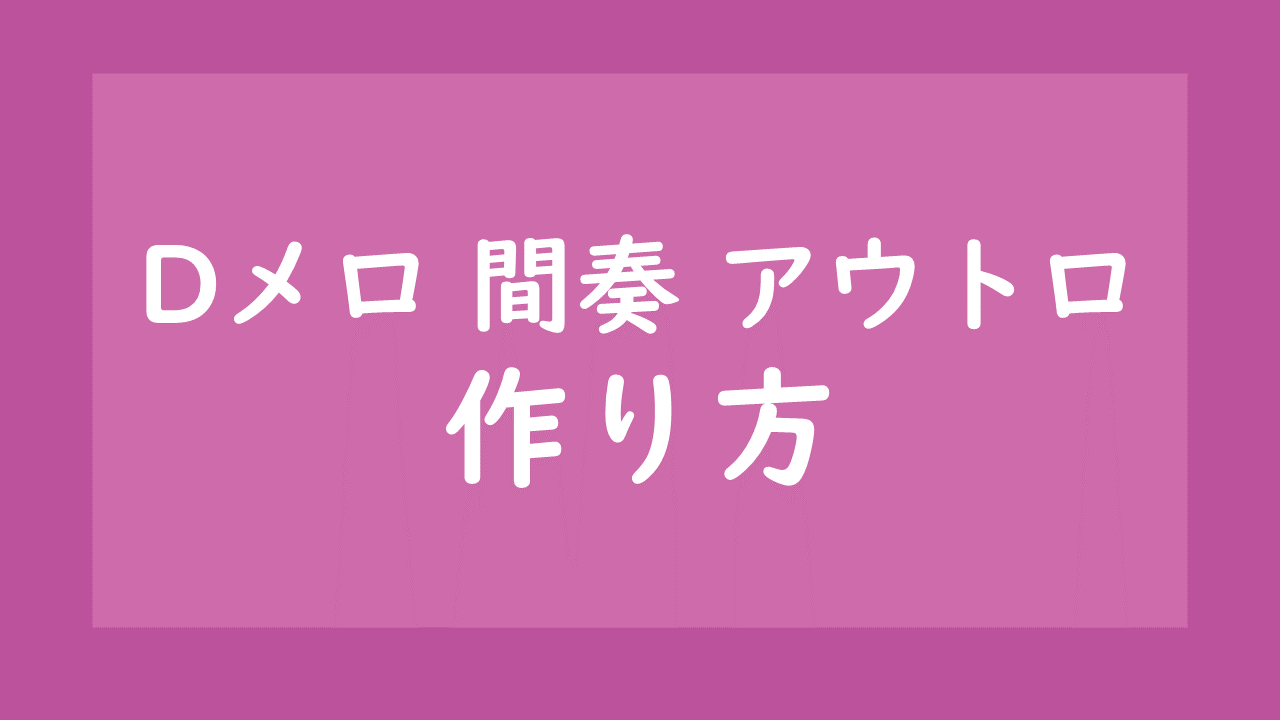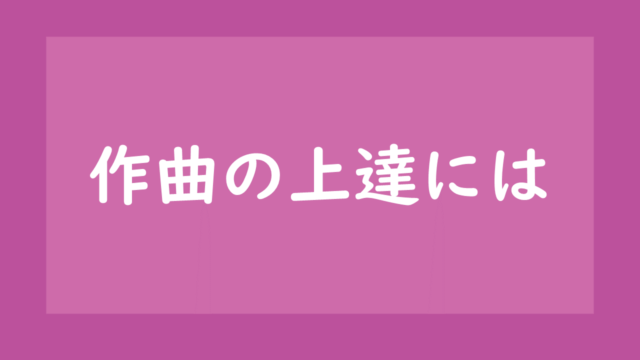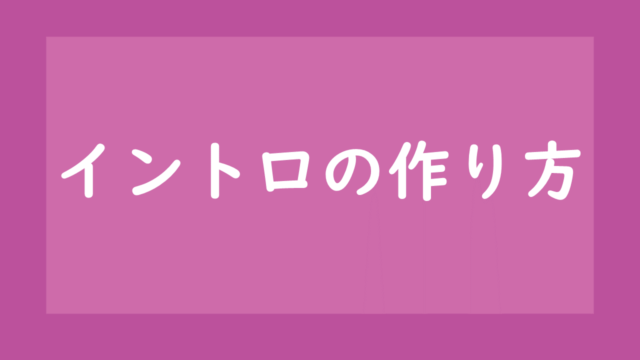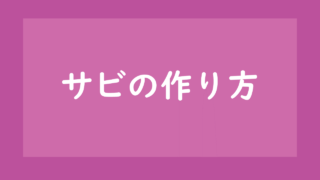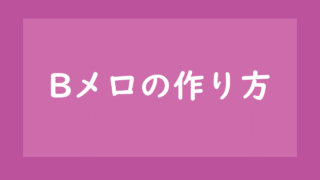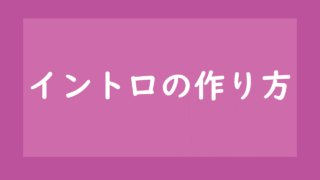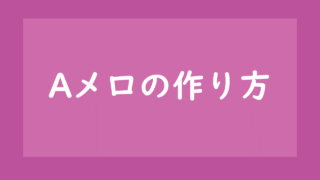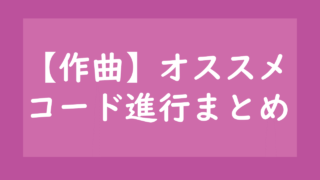・Dメロ(大サビ)の作り方を知りたい
・間奏の作り方を知りたい
・アウトロ(エンディング)の作り方を知りたい
こういった方向けの記事です。
本記事の内容
- はじめに
- 【作曲・編曲】Dメロ(大サビ)の作り方
- 【作曲・編曲】間奏の作り方
- 【作曲・編曲】アウトロ(エンディング)の作り方
■はじめに

こんにちは、作曲日和です。
今回は作曲初心者の方向けに「Dメロ(大サビ)・間奏・アウトロ(エンディング)の作り方」を解説をしていきます。
「曲の作り方」を本やネットで調べると、Aメロ・Bメロ・サビについての情報は多いですが、Dメロ・間奏・アウトロに関してはかなり少ないと感じます。
実際、私自身が作曲を勉強し始めた時、Dメロ・間奏・アウトロに関しての情報が乏しく苦労しました。
この記事が少しでも初心者の方の役に立てば幸いです。
※イントロ、Aメロ、Bメロ、サビについて解説している記事もありますので、あわせてどうぞ。
【作曲・編曲】Dメロ(大サビ)の作り方

Dメロは「2回目のサビの後」や「間奏(ギターソロ等)の前後」に登場するブロックのことで、「大サビ」とも呼ばれたりします。
主な特長としては、
・サビと同等かそれ以上に盛り上げる場合が多い(全く盛り上げない場合もある)
・それまでの曲中に出てこなかった新しいメロディを有する
・テレビ等の歌番組では省略されることが多い
・Dメロが存在しない曲も多くある
です。
それでは、本題に入ります。
① 曲の構成を決める
② 具体的にどんなDメロにするかを決める
③ コード進行を決める
④ メロディを作る
⑤ アレンジ(編曲)
順番に解説していきますね。
① 曲の構成を決める
まず、Dメロを曲のどこに入れるかを決めます。
先ほど述べたように、Dメロは「2回目のサビの後」「間奏(ギターソロ等)の前後」で登場するのが一般的です。
曲後半の構成でよくあるパターンは、
- 2回目のサビ→Dメロ→間奏→ラスサビ
- 2回目のサビ→Dメロ→間奏→落ちサビ→ラスサビ
- 2回目のサビ→間奏→Dメロ→ラスサビ
- 2回目のサビ→間奏→Dメロ→落ちサビ→ラスサビ
- 2回目のサビ→Dメロ→ラスサビ
- 2回目のサビ→Dメロ→落ちサビ→ラスサビ
- 2回目のサビ→間奏→ラスサビ (※Dメロなしパターン)
- 2回目のサビ→間奏→落ちサビ→ラスサビ (※Dメロなしパターン)
- 2回目のサビ→間奏→Bメロを使用したDメロ→ラスサビ
の9つです。
①~④はオーソドックスなパターン
⑤、⑥は間奏がないパターン
⑦、⑧はDメロがないパターン
⑨はBメロをそのままDメロとして使用するパターン(以外と多い。Bメロのなのでサビにスムーズに繋がる)
自分の作っている曲に適した構成を選びましょう。
また、「ラスサビ」と「落ちサビ」についても触れておくと、
ラスサビは「ラストサビ」の略で、最後のサビのことです。
それに対し落ちサビは、「ラスサビ前のテンションを落としたサビ」のことで、「曲にメリハリがつく (Dメロや間奏の勢いのままラスサビに入ると単調になりやすい)」、「クライマックス前の静けさを演出できる」といった効果があります。
落ちサビの作り方
落ちサビは、「ボーカル以外の音を減らして静かな雰囲気にする」が基本です。
・ピアノやアコースティックギターのみ
・ピアノとストリングスのみ
・ドラムは音数少なく、ベースは無しor白玉 …などなど。
落ちサビ前半は少ない楽器で、後半から楽器が増えるを意識して作ると良いです。
② 具体的にどんなDメロにするかを決める
曲の構成(Dメロが入る位置)を決めたら、「具体的にどんなDメロにするか」を考えましょう。
[盛り上がり]
・サビと同じくらい盛り上がるDメロ
・サビよりさらに盛り上がるDメロ
・盛り上げないDメロ
[長さ]
・4~8小節の短いDメロ
・8小節以上の長いDメロ
[世界観]
・感動するDメロ
・明るいDメロ
・淡々としたDメロ
…など。
③ コード進行を決める
次はコード進行を決めます。
他のブロック(Aメロ、Bメロ、サビ)と「同じコード進行」でも「違うコード進行」でも良いですが、それに乗るメロディは新しいものにします。
初心者の方向けに、コード進行の決め方を1つ紹介すると、
・サビの最初のコードがCで始まる場合は、DメロはF始まりにする(Key=C)
・サビの最初のコードがFで始まる場合は、DメロはC始まりにする(Key=C)
このように、サビとDメロの最初のコードを変えるとメリハリがつきます。
また、Dメロを長くしてしまうと曲全体が間延びし、まとまりが無くなりやすいので、最初は8小節程度が良いと思います。
オススメのコード進行はこちらの記事で紹介しています。
④ メロディを作る
コード進行が決まったら、いよいよメロディ作りです。
メロディは②の「盛り上がり」や「世界観」を表現する最も重要なファクターなので、納得いくまで練りましょう。
メロディの終わりも落ちサビやラスサビにスムーズに繋がるように。
また、曲全体を通してのメロディの最高音がDメロで登場する楽曲も多くあります。
メロディは、「高い音が出てくると盛り上がる」ので取り入れてみて下さい。
⑤ アレンジ(編曲)
④までは、曲の骨格(メロディ・コード)についての話でしたが、アレンジ(周りの楽器)も大事です。
・「盛り上がるDメロ」を目指すのなら、楽器数はサビと同等に多く。(「音を詰め込み過ぎてごちゃごちゃ」はNGですが。。)
・「感動系のDメロ」なら全体を覆うようなストリングスが有効。
・「転調」も場面転換の効果がありオススメ。
曲作り全般に言えることですが、既存曲を分析することが上達への近道です。
(Dメロのアレンジにはどんなものがあるのかを知る)
【作曲・編曲】間奏の作り方

続いて「間奏」の作り方を解説していきます。
歌ブロック同士に挟まれた歌のないブロックは全て間奏と言いますが、ここでは「2回目サビ後の間奏」について取り上げます。
J-POPの間奏は「ある楽器がメインとなりメロディラインを奏でる」といったものが殆どです。
ギター、ピアノ、シンセ、ブラス、ストリングス …など
特に間奏が「ギターソロ」である楽曲は多くあります。
(バンド系アーティストの曲はもちろん、アイドルソングやアニソンにも熱いギターソロが入っています)
間奏も他ブロック(Aメロ、Bメロ、サビなど)と同様、作り方に正解はありませんが、今回は初心者の方向けに一例を紹介します。
① 作りたい間奏をイメージする
② コード進行を決める
③ メインメロディを決める
① 作りたい間奏をイメージする
まず最初に、作りたい間奏をイメージしましょう。
ポイントは以下の3つです。
- 間奏前までの曲の雰囲気を踏襲するかどうか
- メインの楽器を何にするか
- 間奏の長さ
イメージが具体的であればあるほど作業しやすくなります。
間奏前までの曲の雰囲気を踏襲するかどうか
世の中の楽曲は「間奏前までの雰囲気を引き継いだ間奏」を有していることが殆どです。
・明るくポップな曲は間奏も明るくポップ
・激しいロック調の曲は間奏も激しいロック調
・ピアノバラードなら間奏もピアノがメイン …など
それに対し、「間奏前までとガラッと雰囲気を変えた間奏」を有する曲もあります。
有名どころだと「ジャニーズグループ」の楽曲。
明るく爽やかなアップテンポ曲の間奏が「激し目のEDM」だったりします。
これは、メンバーの激しいダンスを間奏で披露するためだと考えられます。
メインの楽器を何にするか
先ほど述べたように、間奏は「ある楽器がメインとなりメロディラインを奏でる」が一般的です。
「どの楽器をメインにするか」は作り手の自由ですが、ある程度、曲のテンポ毎に使われる楽器は決まっています。
[アップテンポ]
・エレキギター、ブラス、シンセ…等
[ミディアムテンポ]
・エレキギター、アコースティックギター、ピアノ、ブラス、ストリングス、シンセ…等
[バラード]
・ピアノ、ストリングス、アコースティックギター、エレキギター、シンセ…等
この中のいずれか一つの楽器が、間奏のメインメロディを最初から最後まで演奏する場合が殆どですが、間奏の前半と後半で別の楽器が演奏するパターンもあります。
例1:前半4小節はピアノ、後半4小節はストリングス
例2:前半4小節はピアノ、後半4小節はピアノとストリングスのユニゾン
例3:前半8小節はエレキギター、後半8小節はシンセ …等
間奏の長さ
世の中には「8小節」や「16小節」の間奏を有する楽曲が多いですが、間奏の長さも作り手次第なので自由に決めてOKです。
アイドル系やアニソン系の楽曲は、比較的「8小節」「16小節」構成が多いのに対して、楽器隊も主役であるバンド系アーティストの楽曲には「16小節以上の間奏」も見受けられます。
以下の「Silent Jealousy/X JAPAN」のギターソロは32小節以上あり、ギターソロ(間奏)が本曲の代名詞となっているくらいです。
② コード進行を決める
作りたい間奏をイメージできたらコード進行を決めましょう。
(1) 他ブロックと違う新しいコード進行
(2) 他ブロックと同じコード進行 (流用)
(3) 他ブロックと一部が同じコード進行 (一部流用)
どれでも構いません。
よく、「間奏はAメロやサビと同じコード進行にした方が良いですか?」と聞かれますが、そんなことはなく、自由に決めてOKです。
ただ、間奏の一番最後のコードは次ブロック(落ちサビorラスサビ)への橋渡しになるので、気を配る必要があります。具体的には「着地する(最後のコードをCにする)」「次に繋がっていく感じにする(最後のコードをGにする)」のどちらかです。(他のパターンもあります)
③ メロディを決める
コード進行が決まったら、メロディを作ります。
間奏のメロディは歌のメロディと比べて制約が少ないです。
・楽器で演奏するため、人が歌えないメロディでも良い (「音域」「音符の細かさ」は気にしなくてOK)
・楽器特有の奏法を盛り込める (速弾き等)
もし、思い浮かばない場合は「サビのメロディ(の一部)」を流用することも手です。
【作曲をされている皆様へのお知らせ】
【「作曲・DTM」オンライン無料体験レッスン」を受けてみませんか?】
「椿音楽教室」はオンラインレッスンを開講しており、ご自宅から一歩も出ずに「作曲・DTM」を学ぶことが出来ます。(※2024年現在)
↑↑「プロの作曲家・編曲家を目指している方」「今まで独学でやってきたけど、一度しっかり学びたい方」にオススメです!
【作曲・編曲】アウトロ(エンディング)の作り方

最後は「アウトロ」です。
アウトロは曲の一番最後のブロックで、エンディングと呼ばれることもあります。
アウトロの役割は曲の余韻を残しつつ締めること。
せっかく、アウトロ前までの曲の印象が良くても、最後が微妙なら「曲全体の印象」も微妙になってしまいます。
作曲初心者の方が「アウトロ作り=曲の終わらせ方」に悩むことはよくあります。
そこで今回は、初心者の方に最もオススメなアウトロ手法、「イントロと同じアウトロ」を紹介させて頂こうと思います。
作曲初心者は「イントロと同じアウトロ」がオススメ!
アウトロにもいくつかタイプ(種類)がありますが、中でも「イントロと同じアウトロ」タイプの楽曲はとても多いです。
文字のごとく、既にあるイントロをそのままアウトロとして使うので、初心者の方でも取っつきやすいアウトロ手法です。
ただ、そのままと言っても完全に同じではなく、一番最後の部分に関しては変更が必要になってきます。
→ イントロの一番最後の部分はAメロに繋がるようになっているため、そこを曲が終わるように変更しないといけない。
また、この「イントロと同じアウトロ」は、イントロとアウトロで調(キー)が違ってもOKです。
(「曲中で転調し、元の調に戻らない楽曲」は世の中に多くあります)
最後まで読んで下さりありがとうございました。
【こちらの記事もどうぞ】
【プロが解説】作曲の始め方をまとめました!【DTM・ギター・ピアノ】
【J-POP】作曲家になるにはどうしたらいいの?【独学OKです!】
【作曲】メロディの発想法を11つ紹介!「作れない」を解消!【思いつかない(浮かばない)人向け】
【料金比較しました】ギターレンタルサービス厳選3社!【オススメのギターも紹介】