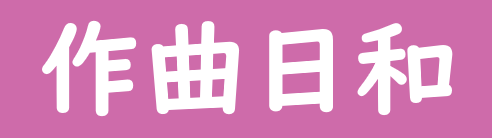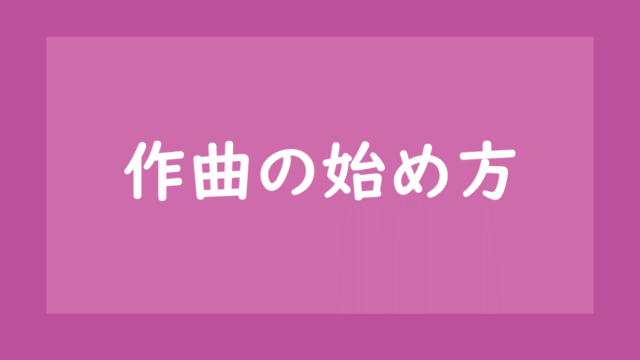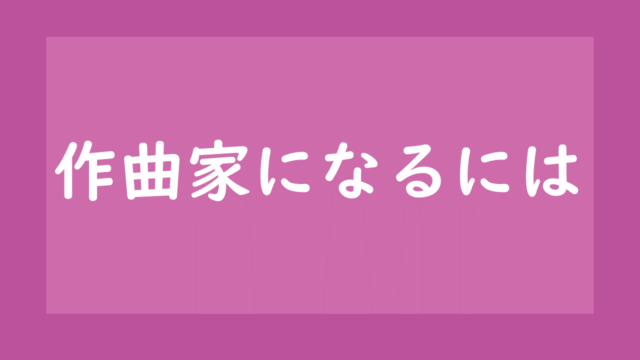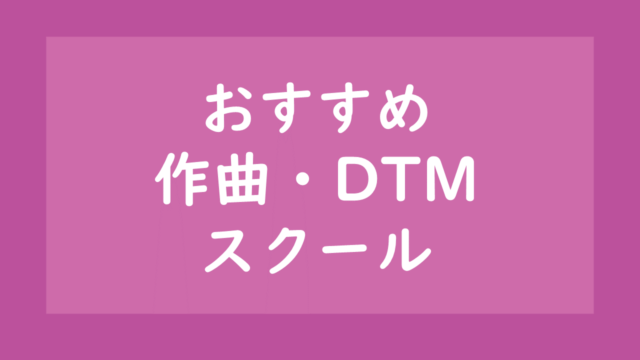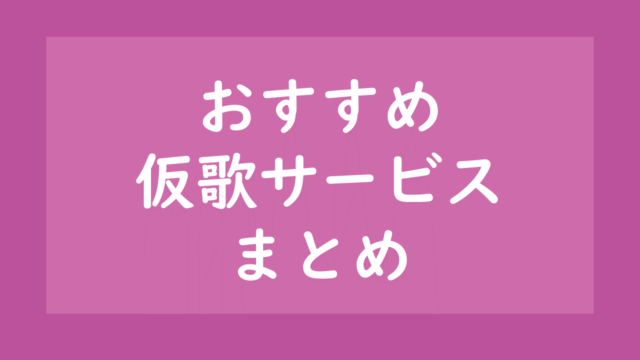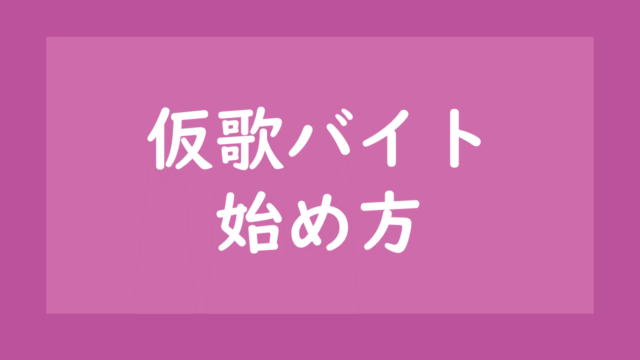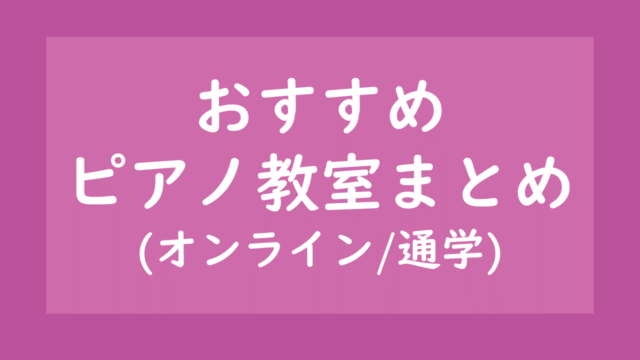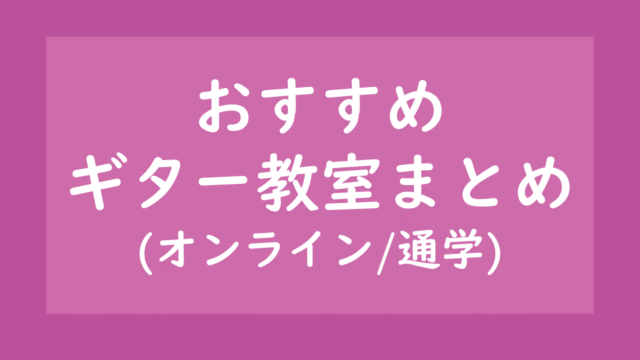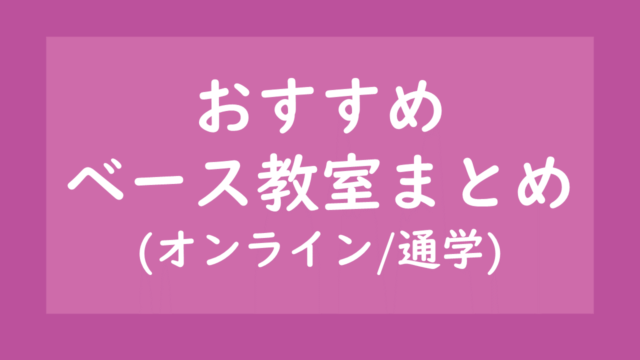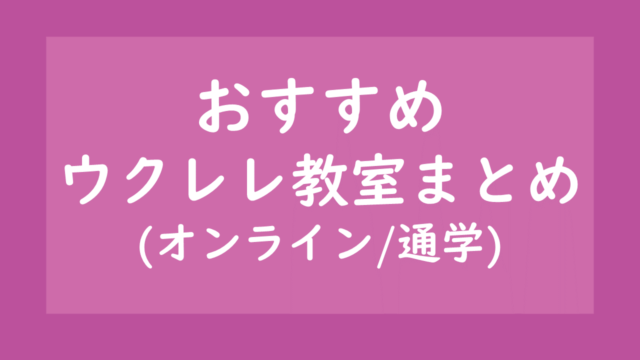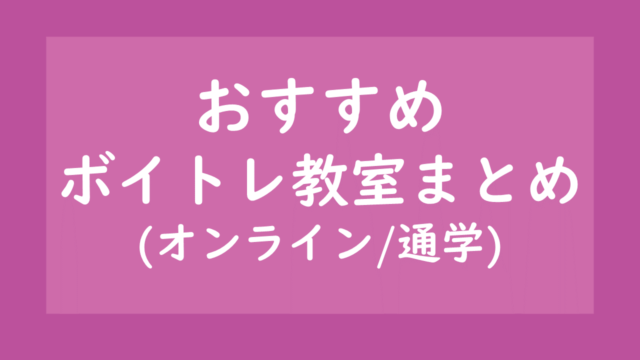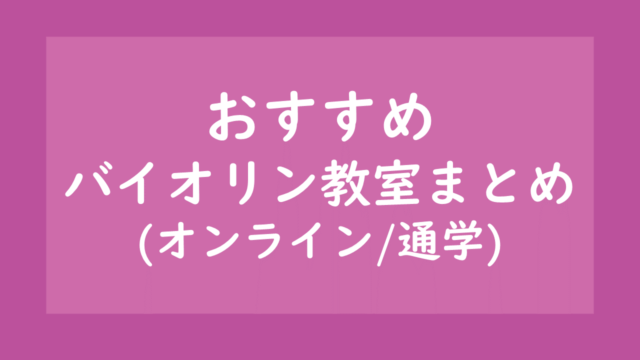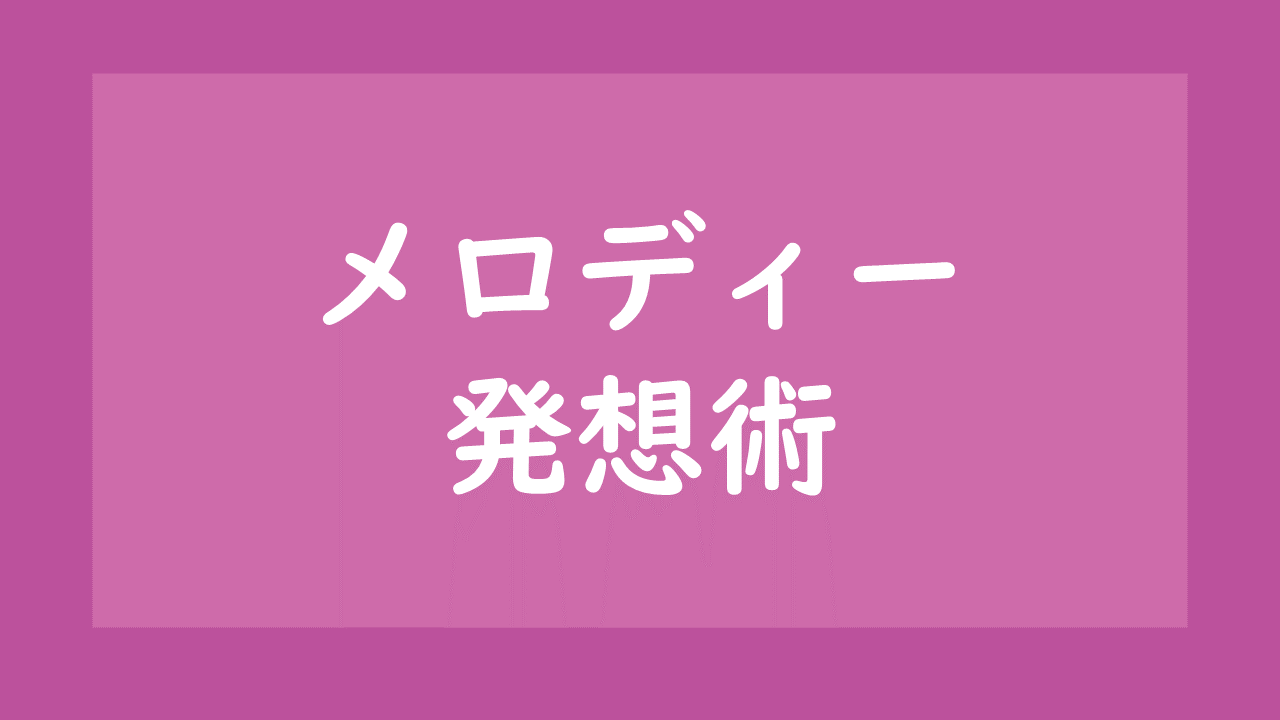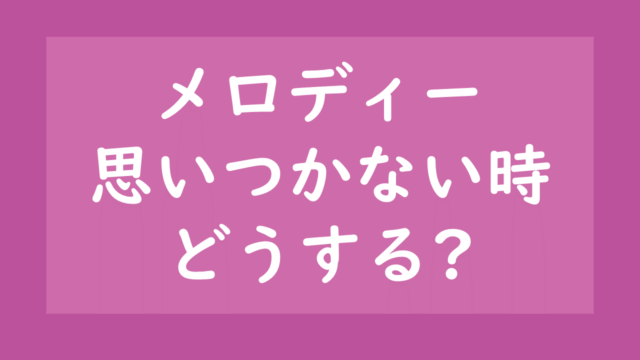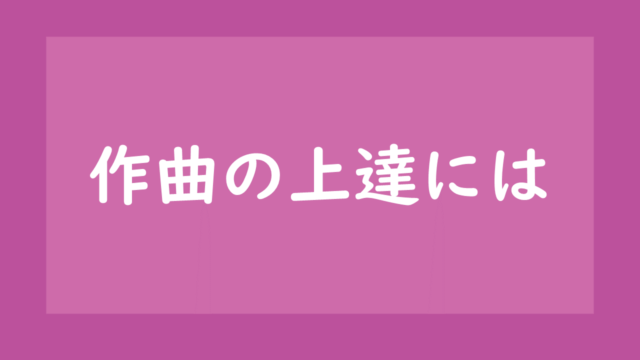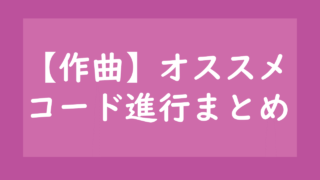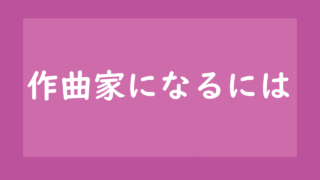・作曲したいけどメロディが思いつかない・・・
・良いメロディはセンスがないと作れないのかな?
・メロディの作り方(考え方)を教えて欲しい
このような方向けの記事です。
本記事の内容
- メロディの発想法を11つ紹介
- 作曲家がよく使うメロディ発想法
- 少し変わったメロディ発想法
■ メロディの発想法を11つ紹介
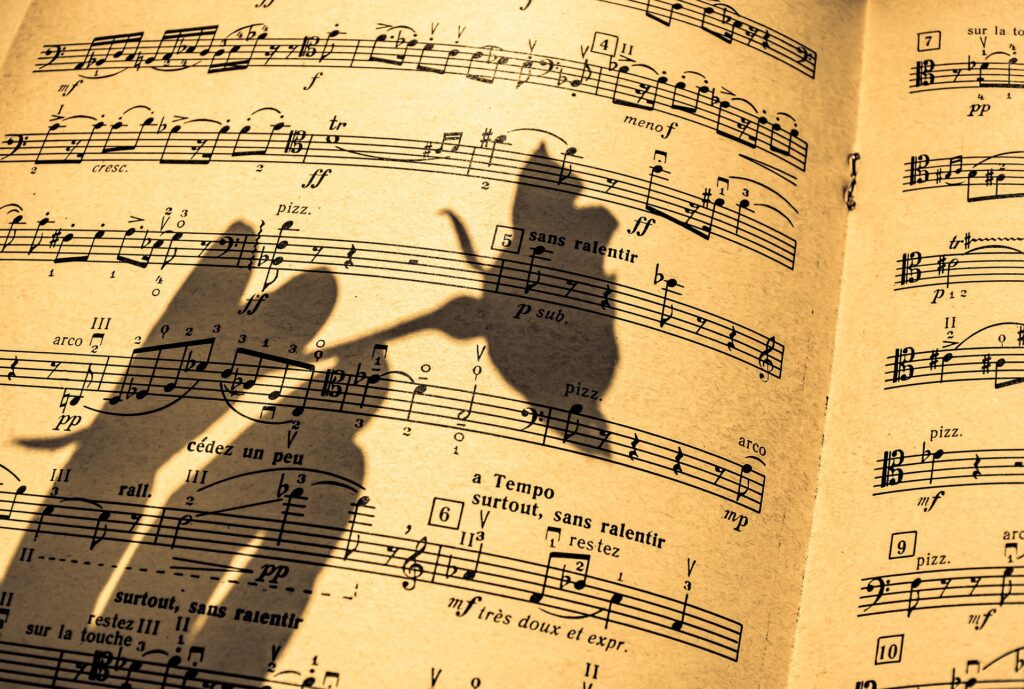
作曲をしている人なら誰しも「メロディ作り」に悩んだことはあると思います。
・「良いメロディが作れない」
・「どこかで聴いたことのあるメロディになってしまう」
・「自分の過去曲と似てしまう」
・「Aメロは出来たけどBメロが思いつかない」
・「そもそも浮かばない」
こういった悩みはプロ・アマ問わず、作曲をやっている以上ついてまわるものです。
ただ、プロ(作曲家)は「作曲することが仕事」ですので「作れないから作らない」は通用しません。
「思いつかない(浮かばない)」状況でも、曲を作り上げられるのが「作曲家」です。その「作り上げられる理由」として一番大きいのは「メロディを引き出すためのアイデアが豊富」ということです。
本記事では「作曲家がよく使うメロディ発想法」と「少し変わった(実験的な?)メロディ発想法」を合わせて11つ紹介していきます。
■ 作曲家がよく使うメロディ発想法

何もない状態からメロディを発想
「メロディ先作曲」です。
何もない状態で鼻歌や楽器でメロディを考えます。
「コードや歌詞が決まっていないため縛りがなく、自由に発想できる」というメリットがある一方、「ありきたりなメロディになりやすい」「メロディの癖が出やすく、自身の過去曲に似てしまう」「初心者の場合、コードを付けるのが難しい」といったデメリットもあります。
コード進行からメロディを発想
「コード先作曲」です。
先にコード進行を決め、そのコード進行をギターorピアノで弾きつつ、メロディを作っていきます。
既にコード進行という道筋(ガイド)があるため、メロディは考えやすいですが、「コードとマッチしないメロディは使えない」といった制約も生まれます。(→ その箇所のコードをメロディに合うものに変更することで対処可)
また、普段使わないコード進行を用意することで「自身の過去曲に似てしまう」を回避できることもメリットとして挙げられます。
トラックからメロディを発想
先にDAW上で伴奏パートを完成させ、そこにメロディを乗せていく手法です。
(コード先作曲の究極系とでも言いましょうか)
コード先作曲の一種ですが、歌以外の全てのパートが鳴っている状態でメロディを考えられるため、「ギターorピアノだけのシンプルな伴奏」では思いつかないようなアイデアが出てきたりします。
難点としては、トラックを作っている段階で脳内にメロディが浮かんでしまい、そこから離れられなくなりやすいことです。(→トラックとメロディ(トップライン)をそれぞれ別の人が作る「コライト」で対処可)
歌詞からメロディを発想
「詞先作曲」です。
先に歌詞を考え、その歌詞にメロディを付けていきます。
何も無い状態でメロディを考えるよりは「ありきたりなメロディ」になりにくく、初心者の方にもオススメの手法です。
歌詞の意味に沿ったメロディが浮かびやすい。
(→「切ない歌詞」には切ないメロディが、「明るい歌詞」には明るいメロディが浮かぶ)
理論的にメロディを発想
理論的にメロディを作る手法もあります。
手法①:メロディのリズムを先に決める
→ メロディは「音程とリズム」から成り立っているので、先にリズムを決めてしまえば、規則性・統一感のあるメロディが作れます。(例:四分音符主体にする、付点音符主体にする 等)
キャッチーな楽曲は、必ずと言っていいほど、メロディのリズムに「規則性・統一感」があります。
手法②:最初の1音を決める
→ 強制的にメロディの最初の1音を決め、続きを考えていきます。
手法③:メロディに制限を設ける
→ 人によってはメロディに制限を設けることで、選択の幅が狭まり、考えやすくなることがあります。
制限は「1オクターブで作る」「ヨナ抜き音階で作る」等です。
仮想ブロックから発想
「仮想ブロック」という言葉は無く、今考えました (笑)
仮のブロック(イントロ、Aメロ、Bメロ 等)を作り、そこから次のブロックのメロディを発想する手法です。
例えば、「サビに向かって行くようなメロディを適当に歌い、それをBメロと見立て、サビのメロディを考える」といった感じです。
この場合、「サビに向かって行くようなメロディ」が「仮想ブロック(仮想Bメロ)」になります。(仮のBメロなので忘れてOK)
他には「楽器で適当にイントロっぽいフレーズ (コード弾きやアルペジオ 等) を弾いて、Aメロを考える」(仮想イントロ)も有効です。
ブロックごとに作り方を変える
こちらは発想法とは少し違うのですが、ブロックごとにメロディの作り方を変えることで、マンネリ解消になります。
例えば、
・「Aメロはメロディ先で作る、Bメロはコード先で作る、サビは詞先で作る」
・「Aメロは楽器で作る、BメロはDAWにマウス入力で作る、サビは鼻歌で作る」
といった感じです。
脳をリラックスさせる
作曲を含め、発想を必要とするクリエイティブな作業には「リラックスした状態の脳」が欠かせません。
リラックスした状態の脳には「アルファ波」が出ており、「ひらめき(発想)」や「思い出す(記憶)」等の現象はこの時に起こります。
脳が緊張状態(作曲しなきゃ!)になっているとアルファ波が出ないので、良いメロディは浮かびにくいです。
アルファ波を出すには「シャワーを浴びる・散歩する・ドライブする」等が有効です。
【こちらの記事もオススメ!】
■ 少し変わったメロディ発想法
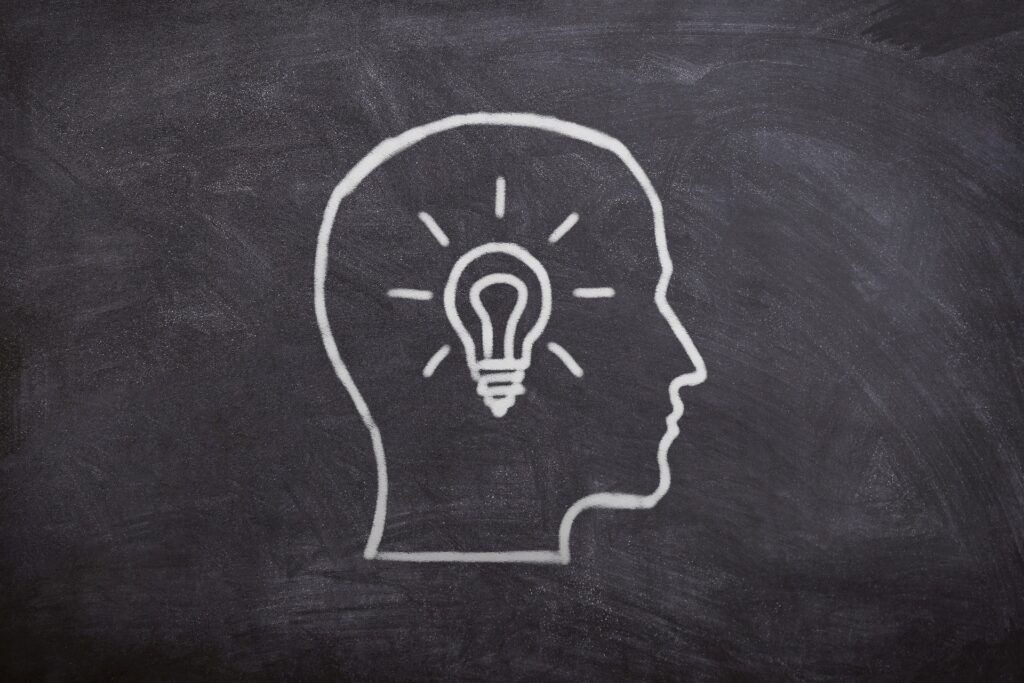
イメージからメロディを発想
イメージからメロディを考えるのもアリです。
① ジャンルやアーティスト名をイメージして作る
例えば、「アイドル風のメロディ」「V系っぽいメロディ」「AKB48風のメロディ」などです。
② お題をイメージして作る
例えば、「雨上がり」「廃墟」「サイクリングロード」「ペンギンの運動会」などです。
知らない既存曲からメロディを発想
既に存在する楽曲からヒントを得てメロディを発想する手法です。
どんな曲でも良いですが、絶対に「自分の知らない曲」を選ぶこと。
知っている曲を選んでしまうと、無意識にその曲のメロディを浮かべてしまうので。
方法は3つあります。
① 知らない曲のイントロを活用して作る (メロディ先作曲)
既存曲のイントロを再生後、イントロ終了直前に停止し、その流れでAメロのメロディを考える。
② 知らない曲のコード進行を活用して作る (コード先作曲)
コードサイトに載っている既存曲のコード進行を、ギターorピアノで弾きながらメロディを考える。
③ 知らない曲の「歌詞」を活用して作る (詞先作曲)
歌詞サイトに載っている既存曲の歌詞にメロディを付けていく。(※メロディが出来たら、歌詞は変更しましょう)
日常の文字からメロディを発想
こちらは詞先作曲の一種ですが、メロディを付けるための歌詞を書く必要がないので手軽に行えます。
日常で目についた文章にメロディを付けてみましょう。
・「本」
・「ネットニュース」
・「新聞やチラシ」
など、ある程度長い文章が書かれているものなら何でも大丈夫です。
(単語や一言とかになると短すぎて厳しい)
■ おわりに

いかがでしたでしょうか?
ご紹介した中で、自分に合いそうな「メロディーの発想法」がありましたら是非、曲作りに取り入れてみて下さい。
最後まで読んで頂きありがとうございました。